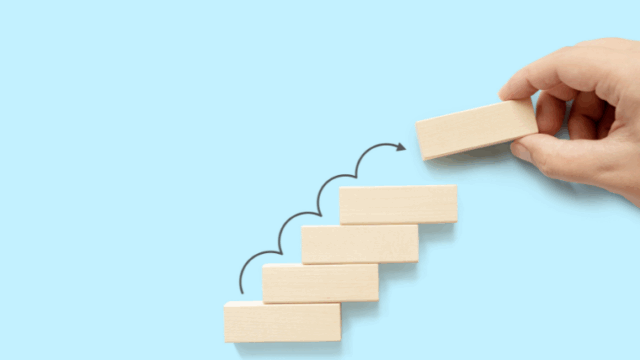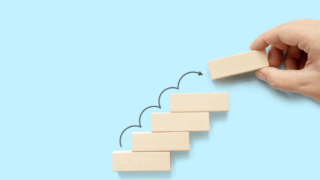「年の差婚、不安って…思ってるの、私だけ?」
最初は安心だったんです。
15歳年上の夫。落ち着いてて、聞き上手で、経済的にも安定してて。
「いや〜大人の男、最高♡」なんて、浮かれてました。
(あの頃の私に“現実はあとからくる”って教えてあげたい)
でも、子どもが生まれて生活がガラリと変わると、
気づけば“余裕のある大人”は、ただただ仕事が忙しい人になってました。
「夫が定年を迎える頃、私…まだ働き盛り?」
「年の差婚 不安」検索ばかり。
老後・介護・教育費・住宅ローン…。
今すぐじゃないけど、ふっと夜になるとやってくる未来の不安。
この記事では、
そんな“検索魔”だった私が「年の差婚 不安」に答えを探して見つけた、
リアルな気づきと、小さな前進の記録をそっとお話ししていきます。
年の差婚、不安なのは“老後”じゃなかった。

年の差婚の不安を“見ないフリ”してきた私へ
「とりあえず今が回ってればいいや」って、見ないフリしてた不安。
不安になって検索するも、
どの記事を読んでもわかってるんだよ〜って言う内容ばかりで解決せずモヤモヤ…
でも実は、その将来の不安は、自分の人生の方でした。
「あなた、このまま夫の人生に合わせて、終わっていいの?」
「“自分の人生”をちゃんと考えてあげてる?」
年の差婚の不安って、「老後に備えましょう」だけじゃ片付かない。
私が向き合うべきだったのは、私がどう生きたいのかという問いでした。
住宅資金の現実|ローン審査と将来設計の落とし穴

夫の年齢が住宅ローンにどう影響する?
年の差婚あるあるのひとつが、「住宅ローンが思ったより通らない問題」
住宅って、夫の収入が安定していればどうにかなると思ってました。
でも、実際に審査してみると——
「完済年齢が80歳を超えると難しいですね」とサラッと言われる。
がん保険なども持病があると入れなかったり、
金利が高くなったり、いろいろ障害はつきものです。
ちなみに、住宅金融支援機構のフラット35では、
完済年齢の上限は「80歳まで」が条件とされています。
(※出典:住宅金融支援機構 フラット35|融資のご案内)
つまり、夫が50歳を過ぎていれば、
ローンを組める年数は「30年ローン」どころか
「15〜20年ローン」が限界になる場合ある。
そして、短期間ローンにすれば当然、月々の返済額は爆上がりです。
老後も家の支払いが続くという現実
仮に、ローン審査が通ったとしても安心はできません。
夫が定年を迎える頃、
まだローンがガッツリ残ってるっていうケースもありますよね。
年の差婚では、“定年=ローン完済”にならないのが普通です。
でも、子どもの教育費が一番かかる時期って、ちょうどその頃なんです!
大学入学+ローン返済+夫の収入減。
このトリプルパンチ、想像しただけで怖くないですか?
「家が欲しい」は夢だったけど、 「老後も家の返済がある」は現実でした。
私たちに必要な「家の持ち方」を考える
「家を持つこと=安心」と思ってました。
でも、年の差婚というライフステージでは、“持ち方”を見直す必要があると感じています。
たとえばこんな選択肢も、アリかもしれません:
- 頭金を多めにして、ローン年数を短くする
- あえて中古住宅やコンパクトな家を選ぶ
- 将来の売却・住み替えも前提にした家選び
- ローンは夫単独ではなく、自分も一部負担する前提で考える
ポイントは、「今の収入」だけで考えないこと。
夫婦の将来・老後・教育費までを含めて、無理のないプランを立てることが、
年の差婚で“安心して暮らす”ための一歩になると実感しています。
教育資金|子どもの進学と老後がかぶるという罠

「教育費ピーク=夫の定年」の衝撃
「教育費って、私たちにはまだ先の話でしょ?」と思ってました。
でもある日、冷静に計算してみたんです。
末っ子が子どもが大学に入学する年と、夫が定年を迎える年。
…見事にドンかぶりでした。
しかも、教育費って大学4年間だけじゃありません。
文部科学省の調査によると、幼稚園〜大学までの学費合計は、
- 公立:約1,000万円
- 私立:約2,000万円以上
(※出典:文部科学省|教育費負担 )

「子どもが巣立つタイミング」=「家計が最もきつくなるタイミング」
しかも夫の収入は定年で、再雇用となると収入もガクッと減少します。
これって…人生設計の落とし穴じゃない?と思いました。
どう備える?教育資金と家計の両立
じゃあどうする?って話ですよね。
現実的な対策は3つあります:
- 学資保険などでの計画的な積立
- 児童手当などを「使わず貯める」仕組みにする
- 夫の収入だけに頼らず、自分にも収入源を持つ
「夫が高収入=安心」ではないという現実が、年の差婚にはあります。
むしろ、夫の定年後に“自分が子どもの学費を支えていく”可能性も高いんです。
「支え合う」の意味が年代によって変わる——それを実感しました。
奨学金・制度・積立…選択肢は意外とある
とはいえ、「うちそんなに貯金できないんだけど…!」って人も多いはず。
でも大丈夫。
教育費には意外と多くのサポート制度があります:
- 日本学生支援機構の奨学金制度(第一種・第二種)
- 給付型奨学金(世帯収入によっては返済不要)
- 高校無償化制度
- 積立NISAやiDeCoで“将来用”の貯蓄をスタートする
全部使う必要はありません。
でも、「何が使えるか」を知っておくことが、家計の安心につながります。
未来は読めなくても、「備える準備」は今から始められるんです。
老後資金が不安すぎる|でも漠然としすぎて動けない

いくら必要?老後資金のざっくり目安
「老後って、どのくらいお金かかるの?」
正直、私もずっと“なんとなく不安”止まりで、ちゃんと調べてなかったんです。
でもある日、SNSで見た「老後2,000万円問題」というワード。
- 夫婦2人で生活するには、月平均約26万円
- 年金だけでは約5万円不足 →
このままだと、20年で約2,000万円足りなくなるという試算
(※出典:生きる」が 代に? – 厚生労働省)
老後って、ただ年金でのんびり暮らすイメージだったけど…
「お金かかるじゃん」って、内心めちゃくちゃ焦りました。
「夫の年金だけ」は危険信号
「まぁ、うちは夫が厚生年金入ってるし、大丈夫かな〜」って思ってた時期もあります。 でも、年の差婚の場合、
夫が年金を受け取っている期間=自分がまだ現役の期間でもある。
つまり、“収入格差のある2人暮らし”が10年近く続く可能性があるんです。
さらに、厚生労働省のデータによると、年金の平均受給額は👇
- 国民年金(自営業など)→ 約5.6万円/月
- 厚生年金(会社員)→ 約14.6万円/月(男性)
(※出典:厚生労働省|令和4年度厚生年金保険・こくみんねんきん国民年金事業の概況)
夫婦で合わせて20万円前後。
でもこれ、手取りじゃないし、増えることもない。
そのうえ、医療費・介護費・住居費はむしろ増えますよね。
「夫がいれば安心」じゃなくて、
「夫婦ふたりで乗り越える設計」じゃないと安心は作れない。
そんな現実が、じわじわと見えてきました。
「自分にも収入源を」と思い始めた瞬間
それまでの私は、ずっと「夫が稼ぐ人、私は支える人」って思ってたんです。
でも、未来を考えたときに初めて思いました。
「私が“誰かに頼らず収入を得る力”を持てたら、きっと心が軽くなる」
とはいえ、いきなり「起業!」「キャリアアップ!」なんて無理。
私にできるのは、まずは今の延長線でできそうなことを知ることからでした。
老後資金が不安で検索してた私が、
「収入を増やす=選択肢が持てる」って思えた瞬間、
ちょっとだけ未来の不安が“希望”に変わった気がします。
年の差婚で老後に気をつけたい3つのこと

介護と孤独は“いつか”じゃなく“いつでも”やってくる
「介護なんて、まだまだ先の話でしょ?」
と思っていた私に、ある日突然やってきた“現実”。
年の差婚では、
パートナーが介護を必要とする時期が、
普通の夫婦より早く訪れる可能性が高いんですよね。
内閣府の「高齢社会白書」によると、
- 要介護となる平均年齢は75歳前後
- 介護期間の平均は約4年11か月 (※出典:内閣府|令和5年版高齢社会白書)
60代で介護生活に入る人もいれば、
70代で「見送る側」として残されることもある。
そしてもうひとつ見落としがちなのが、「孤独」
「夫と一緒に過ごせる時間が長くてラッキー」と思っていたのに、
ふと気づくと、パートナーを見送った後に“長いひとり時間”が待っているという現実。
それって、正直ちょっと…いや、かなりこわい。
体力・メンタル・収入、すべてに備えが必要
老後って、資金だけじゃ乗り越えられない。
必要なのは、「3つの備え」
- 体力の備え:一人で動ける期間を延ばす
- メンタルの備え:孤独・喪失・不安と向き合う心の土台
- 収入の備え:足りない分を“補う”安心感
若いころは「なんとかなる」が口ぐせだった私も、
子育てと夫の年齢差、将来の生活をリアルにイメージしたとき、
「なんとかする」ための準備が必要だと気づきました。
年の差婚では、“想像より早く”老後のステージがやってくる。
だからこそ、心と体とお金、それぞれに“ちょっとずつでいいから備える習慣”が大切です。
「夫婦一緒に老いる」ことの現実と向き合う
年の差婚における理想の老後って、実はすごく特殊です。
年が近い人と結婚をすると
同じタイミングで仕事をリタイアして、 のんびり旅行して、孫と遊んで…って。
でも歳の差だと、多くの場合タイミングがズレてるんです。
- 夫:定年後のんびりタイム → 私:仕事や子育てでまだまだ現役
- 私:子ども手が離れて自由な時間 → 夫:介護フェーズ突入
「夫婦一緒に老いる」って、実はすごく難しいことなんだと気づきました。
だからこそ、「今」から少しずつ意識する。
- 自分の人生設計
- 一人時間との付き合い方
- 自分の“老後の幸せ”の定義
年の差婚はハードモードかもしれないけど、
気づいて備えられる人は、ちゃんと“自分のペースの幸せ”をつかめると思います。
夫の定年後、“私の人生”をどう生きる?

「定年=自由時間」ではない現実
「夫が定年になったら、やっとゆっくりできるかな〜」なんて思ってました。
むしろ、「え、ずっと家にいるの?」と驚く日々の始まりが待ってます。
- 三食の用意
- 一緒にテレビ
- 「今日なにする?」って毎日聞かれる
- 「あれ取って」「これどこ?」が10倍に
正直、自由になるどころか、“夫がずっといる不自由”が始まる感覚が想像できました。
家にいてくれるのはありがたい。
でも
「なんで今、私のルーティンに割り込んでくるの?」
っていう地味なストレス、ありそうですよね(笑)
「夫と一緒にいる時間が増える恐怖」をどうする?
もちろん、夫のことは嫌いじゃないです。
子どもが巣立って、
やっとひと息つける…と思ったら、 今度は夫が「今日どうする?」と1日中家に。
え?“静かな老後”って、どこ行った?ってなる予感しかしてないです。
これは「仲悪い」とかじゃなく、自分の時間がなくなる不安なんですよね。
- 「一人の時間が恋しい」
- 「毎日一緒はしんどい」
- 「息抜きが“悪いこと”みたいでツラい」
年の差婚じゃなくてもある問題だけど、
定年のタイミングがズレる年の差婚では特に大きい。
「私、何をして生きたいんだろう?」と初めて考えた日
それまでは「夫のサポート役」「家族の裏方」として動くことが当たり前だった私。
でもある日、夫が「退職したら、しばらくゆっくりしたいな」と言った瞬間、
ふと思ったんです。
「あれ、私って…これから何するんだろう?」
子どもが手を離れ、夫はリタイア。
じゃあ私は“自由”になったのかというと、なぜかモヤモヤだけが残りそう。
- 趣味もない
- 友だちと会う時間も少ない
- キャリアもない
- そして、収入もない
これって自由じゃなくて、“空白”かもしれない。
でも、そこでやっと考え始めました。 「私の人生、ここからどう生きたい?」って。
年の差婚は、相手に合わせることが多い。
でも、自分に目を向けるタイミングは、意外とこの「定年のあと」なのかもしれません。
選べる働き方が“年の差婚 不安”を変えた

「働きたいけど、今さら何ができるの?」という壁
「収入源を持とう」
「自分の人生を生きよう」と思ったものの…
いやいや、そう簡単にはいきません。
- スキルもキャリアもない
- 子どもがまだ小さい
- ブランク長いし、自信ない
- そもそも“私にできること”が思いつかない
っていうか、今さら新しいことなんてできる?
そんな不安で、検索魔は再発しました(笑)
「年の差婚 不安」から「主婦 在宅仕事」「スキルゼロ 稼ぐ方法」へ。
検索履歴がもはや“人生に迷ってる人”そのもの。
スキルゼロからでも始められる“収入づくり”って?
そんな中で見つけたのが、
「Webマーケティング」という働き方。
最初は「え?マーケティングって、企業のプロがやるやつじゃないの?」と思ってました。
でも調べてみたら、今は在宅で学べて、スマホ1つでも始められることも多くて驚き。
- SNS運用サポート
- ブログで広告収入
- 企業のInstagram代行
- LINE公式アカウントの構築サポート
あくまで本の一例で他にもたくさんあります。
もちろん、簡単ではないです。
でも、「できることがある」と気づけただけで、漠然とした不安が少し薄れました。
私が選んだのは、“在宅でできるWebマーケ”でした
今は、ワンオペ育児で仕事と家事と育児の両立に懸念していて…
将来夫の老後の介護ができて、
“在宅で学べて、働けて、収入につながるそんなのあるのかな?っと調べついたのが、
”Webマーケティングでした。
- 家事や育児の合間に学べる
- パートよりも柔軟に時間が使える
- 「やりがい」も「感謝される仕事」も感じられる
- なにより、自分にちょっとずつ自信が持てるようになった
年の差婚の不安って、
最終的には「私はどう生きる?」という問いに向き合うことだったんだと思います。
選択肢を知るだけで、人生は変わる。
だから、もし今あなたが夜中に「年の差婚 不安」と検索していたら、
この記事が、少しでも“未来の不安を減らすヒント”になったら嬉しいです。